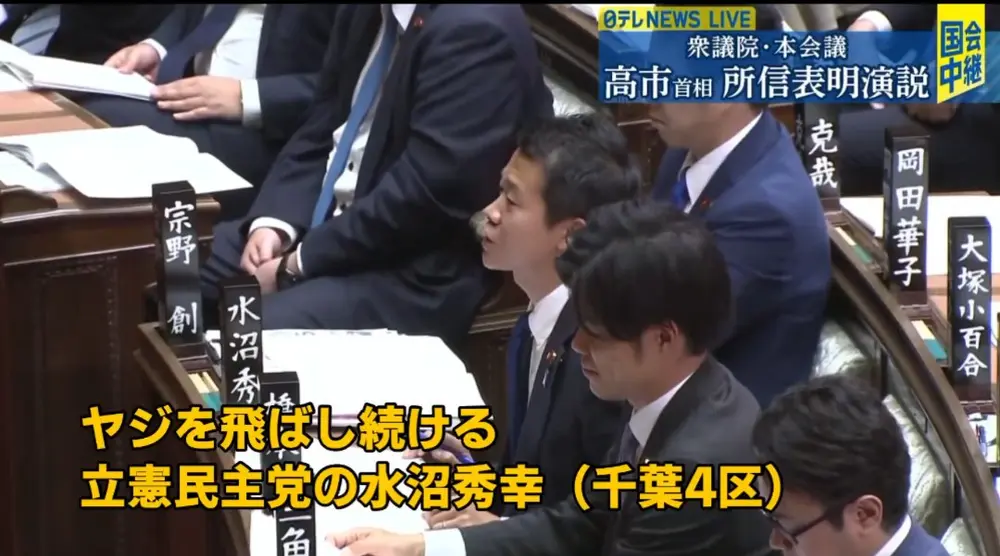大阪市内で中国系とみられる法人が在留資格の取得要件厳格化の直前に倍増していたという
これほど露骨な「駆け込み起業」の実態を目の当たりにすると
わたしたちの税金で整備された制度が
本来の目的とはかけ離れた使われ方をしていたことに憤りを感じずにはいられない。
数字が物語る制度の歪み
データを見れば一目瞭然だ。今年9月、資本金500万円で設立された法人は786社。前月の374社から実に倍増している。しかもそのうち4割の代表者の自宅が中国にあるというのだから、これはもう起業支援というより移住の抜け穴として機能していたと言わざるを得ない。
在留資格「経営・管理」は平成27年、起業意欲のある外国人を受け入れて日本の技術革新や成長を促進させる目的で創設された。その理念は素晴らしいものだったはずだ。実際、真面目に事業を立ち上げ、日本経済に貢献してくれる外国人起業家もたくさんいるだろう。しかし制度の甘さを突いて、実体のないペーパーカンパニーを設立するケースが多発していた。
わたしは思う。ルールをきちんと守って起業した外国人の方々は、この状況をどう感じているか。彼らこそが一番、不公平さを感じているのではないだろうか。
遅すぎた対応だが評価はしたい
出入国在留管理庁は10月16日、改正省令を施行した。資本金の引き上げを500万円から3000万円へ。さらに日本人や永住者など常勤職員を1人以上雇うことも義務付けられた。これは大きな前進だと評価したい。
ただし、正直に言えば遅きに失した感は否めない。令和6年末時点で、経営・管理の資格で滞在する中国人は2万1740人。このなかにどれだけの実体のない会社が含まれているのか。大阪市内だけで直近2年間に設立された法人を見ても、中央区が1065社、西成区が756社と、特定のエリアに集中している。これほどわかりやすい偏りがあったのに、なぜきょうまで放置されてきたのだろうか。
制度を悪用する人々の行動力は驚くほど速い。情報は瞬時に拡散され、抜け穴があればすぐに利用される。その一方で、行政の対応はどうしても後手に回ってしまう。この構造的な問題をどう解決していくか、真剣に考えなければならない時期に来ているのだ。
本当に必要な起業家を見極める仕組みを
わたしたちが本当に受け入れたいのは、日本で事業を成功させたいという強い意志を持ち、雇用を生み出し、税金を納め、地域経済に貢献してくれる外国人起業家である。国籍は関係ない。日本の法律を守り、誠実に事業を営んでくれる人なら、喜んで迎え入れたい。
しかし今回の大阪の事例は、その理想とはあまりにもかけ離れていた。制度の隙間を狙った移住目的の駆け込み起業。これでは制度そのものへの信頼が揺らいでしまう。
改正後の運用がきちんと機能するかどうか、わたしたちはしっかりと見守る必要がある。資本金を引き上げただけで問題が解決するわけではない。事業の実態があるか、継続的な経営がなされているか、定期的なチェック体制も不可欠だろう。
外国人材の受け入れは、これからの日本にとって避けて通れない課題である。人口減少が進むなか、優秀な人材に来てもらうことは経済成長のためにも必要だ。だからこそ、制度が適切に運用され、本当に必要な人材を見極められる仕組みを整えることが重要なのである。ザルのような制度では、誰も幸せにならない。そのことを、きょうの報道は改めて教えてくれている。